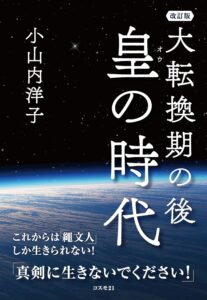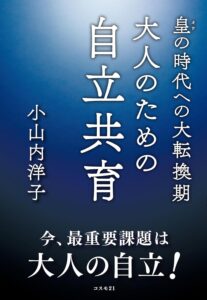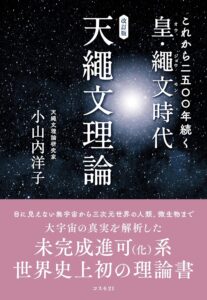天縄文理論の小笠原さんに教えていただいた経済の話。
経済というのは、大きな川の流れのようなもの。エネルギーの川である。
川の真ん中に手を突っ込めば大きな流れ(お金)を掴むことが出来る。
端っこの流れの緩いところはエネルギーが小さく、渦巻いているようなところ、或いは溜まっている澱みなどではエネルギーがあまり動かない。
貯蓄をするというのは、その澱みに手を突っ込んでいるようなもので、お金のエネルギーが回っていかない。
小山内さんの本によると、前時代のお金と天縄文時代のお金は帯びているエネルギーが違うという。
ちなみに、天縄文時代では「経済」ではなく「恵財」というらしい。
ということは、前時代の経済の川と天縄文時代の恵財の川は別のところにあるのだろう。
そして、前時代の経済の川は次第に枯渇していくのだろう。
だとすれば、いつまでもそこに手を突っ込んでいてはいけない(いや突っ込んでいるのはその人の自由だけど)。
また、エネルギーというものは、まず出さないと入ってこない。呼吸と同じである。
深呼吸しようといきなり息を吸っても吸えない。まずは息を吐ききることで、自然に胸いっぱいに吸い込むことが出来る。
自ら循環を作っていくには、まず出力することが大事というわけだ。
しかも、渋々出していては良いエネルギーは循環してこない。ワクワク、喜んで出すことがポイントである。
ついでに景気の話にも触れておこう。
景気が良いとか悪いとか言うが、たとえ景気が悪いと言われているときでも、儲かっているところは必ずあるし、景気が良いときでも、儲からないところもある。
100%の人が同じ状況であることはあり得ないわけで、景気に左右される必要はない。
必要なのは、知恵と独自性である。